
川島大知
2018年3月に「害獣プロテクト」を立ち上げ。
建築のプロとしての知識と、現場経験に裏打ちされた判断力を活かし、単なる駆除業者では実現できない「住まいを守る害獣対策」を提供している。
CONTENTS
[ネズミ駆除]
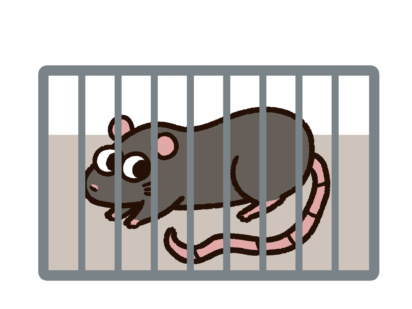
マンションでのネズミ被害に悩んでいませんか?
本記事では、初心者向けにネズミの種類や被害のリスク、予防法、駆除の方法、費用や業者選びまでをわかりやすく解説します。
安全で快適な住まいを守るための知識を身につけましょう。
目次
マンションという集合住宅は、一見するとネズミのような害虫が入り込みにくいように感じるかもしれません。
しかし、実際には東京都内のような都市部を中心に、分譲マンションでも賃貸マンションでもネズミの被害は増えつつあります。特に高層の部屋であっても油断は禁物で、ネズミは思わぬ場所から室内へ侵入してくるのです。
ネズミがマンションに侵入する主な理由は、まず「食べ物の存在」が挙げられます。
台所に食べ残しが放置されていたり、ベランダに出したゴミ袋からニオイが漏れていたりすると、ネズミは敏感にそれを察知し、室内までやってくる可能性があります。特に網戸がきちんと閉まっていなかったり、電気をつけっぱなしにして外出していると、ネズミが入りやすい環境を自ら作ってしまっているケースも少なくありません。
また、マンションの構造上、「隙間からの侵入」も多く見られます。
配管のすき間や壁の亀裂、小さな通気口など、ラットや黒いネズミのように身体の柔らかい種類は、わずかな穴でも簡単にすり抜けて室内へ入り込みます。
これに加え、「共用部分の管理不足」もネズミを引き寄せる要因になります。エントランスやゴミ置き場の清掃が不十分だと、ネズミにとって居心地のよい住処となってしまうのです。
これらの理由を理解することで、なぜマンションという密閉性の高い建物にもネズミが入り込むのか、その現実的な背景が見えてきます。
ネズミは単なる不快な存在にとどまらず、私たちの健康に深刻なリスクを及ぼす可能性があります。
最も大きな懸念は「感染症のリスク」です。
ネズミは、ハンタウイルス、レプトスピラ症、さらには鼠咬症(そこうしょう)など、多くの病原菌を媒介することで知られています。特にネズミの糞や尿に含まれる病原体が乾燥し、それが空気中に舞い上がることで、吸い込んだ人が感染するケースもあります。
さらに、ネズミの排泄物や体毛、さらには死骸は「アレルギーの原因」となり得ます。小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、ダニやカビと同様に、ネズミによるアレルゲンの影響が懸念されます。
加えて、「食品の汚染」も深刻な問題です。
ネズミがキッチンに侵入して食材に触れることで、食中毒や雑菌による体調不良が起きやすくなります。足音が気になるだけでなく、目に見えないリスクが潜んでいるということを、改めて認識しておく必要があるでしょう。
マンションでネズミを見つけた方は、『高層階だから安心だと思っていた』『管理会社に相談したけど対応してもらえなかった』と不安を口にされることが多いです。実際に伺ったお宅では、共用の配管スペースを通じて台所に侵入しており、住人の方は『自分の部屋と繋がっていると思うと怖くて眠れなかった』と話されていました。
私たちが大切にしているのは、駆除だけでなく“二度と同じ思いをさせないこと”。マンションは建物全体がつながっているため、一人で悩まず、早めに専門家に声をかけていただくことが解決への一番の近道です!

害獣プロテクト
川島大知
マンションで見かけるネズミは、主に「ドブネズミ」「クマネズミ」「ハツカネズミ」の3種類です。それぞれに異なる特徴や行動パターンがあり、対策のポイントも変わってきます。
ここでは、それぞれのネズミについて詳しく解説します。
ドブネズミは、体長が20cm以上に達することもあり、成体では体重が300gを超えることもある大型のネズミです。
その名の通り、水辺や下水道といった湿った環境を好み、配管を通じてマンションの地下や共用部分に侵入するケースが多く見られます。
特に段ボールの隙間や、住人の目が届きにくい場所にひそんでいることが多く、目撃する機会は少ないものの、かじった痕や糞などの痕跡で存在に気づくことがあります。
警戒心が強く、行動は主に夜間。昼間に姿を見かけることがあれば、すでに個体数が増えている可能性もあります。環境によって生息しやすさは異なりますが、東京都内のように下水インフラが複雑な地域では特に多く報告されています。
ドブネズミの侵入を防ぐには、配管や通気口のチェックと清掃を定期的に行うことが有効です。
クマネズミは、体長が約20〜25cmほどで、尾が体よりも長いのが大きな特徴です。
性格はドブネズミとは異なり、非常に好奇心が強いため、物をかじったり、食べ物を持ち去ったりする習性があります。このため、キッチン周辺や食品庫に出没しやすく、放置された食材が被害に遭うことも。
また、巣作りは屋内の高い場所を好み、マンションでは天井裏や壁の内部、収納スペースなどに棲みつく傾向があります。
神奈川県など都市部でも被害が報告されており、クマネズミがかじった電気コードによる火災事故なども報告されています。作業時に天井裏で動く足音や、コウモリやアライグマと間違われるケースもあるため、早めの対応が大切です。
ハツカネズミは、体が非常に小さく、体重もわずか20g前後と軽量です。
見た目はかわいらしい印象を受けるかもしれませんが、その繁殖力は極めて高く、2025年現在でもマンション内で急速に個体数を増やしてしまう事例が後を絶ちません。
このネズミの最大の問題点は、わずかな隙間からも侵入できること。
網戸のわずかな隙間や、家具の裏などに棲みついてしまうため、放置すると「困りもの」の存在になります。性格はおとなしく、動物としての俊敏さはやや劣りますが、その分、簡単な罠でも捕獲しやすいという特徴があります。
ハツカネズミの対策としては、隙間を徹底的に塞ぐことと、食品の密閉管理が基本です。個体数が少ないうちに発見し、早期に対応することで、大きな被害を防ぐことができます。
現場で調査をしていると、同じマンション内でも“部屋によって出るネズミの種類が違う”ということがあります。地下のゴミ置き場や配管スペースで見つかるのはドブネズミが多いのですが、上層階に行くとクマネズミが天井裏に巣を作っていることもあります。ある時は、1階で大型のドブネズミを捕獲した直後に、10階の部屋で小さなハツカネズミの被害相談を受けたこともありました。
種類ごとに行動パターンが違うため、住民の方が『足音はするのに姿が見えない』『糞の大きさが思っていたのと違う』と混乱してしまうのも無理はありません。特にクマネズミは警戒心が強く、捕獲器を置いても簡単にはかからないため、粘り強い対応が必要です。
こうした現場を経験すると、“ネズミ=ひとくくり”ではなく、それぞれの特性を理解して対策することがいかに大切かを痛感します。住民の方にとっても、種類を見極めて早めに行動することが、安心を取り戻すための大切な第一歩になります!

害獣プロテクト
川島大知
ネズミの侵入を未然に防ぐためには、日々の対策が欠かせません。
マンションという集合住宅では、わずかな隙間やゴミの放置が原因となり、あっという間にネズミの住処になってしまうことがあります。
ここでは、隙間の対策、食材やゴミの管理、そしてネズミが嫌う香りの活用について解説します。
ネズミの侵入経路として最も多いのが、建物の小さな隙間です。
特に外壁の亀裂や天井裏、通気口のまわり、ガラス戸やサッシのわずかなすき間など、気密性の低い箇所から入り込むケースが目立ちます。配管の穴やエアコンの配線まわりも、侵入ルートになりやすいため注意が必要です。
まずは、これらの「隙間を特定」することが第一歩です。
明るい時間帯に建物の外周を確認し、小さな穴やひび割れがないかチェックしましょう。ネズミは体が柔らかく、わずか2cm程度の隙間でも入り込めるため、思わぬ場所から入ってきてしまいます。
対策としては、金属製のネットや、刺さらず手軽に使えるシーリング材で「隙間を塞ぐ」ことが効果的です。
ガラス周辺や天井付近の伸びた亀裂など、気になった場所は放置せず、早めに補修することが大切です。また、定期的に点検を行い、新たな隙間ができていないか確認することが、長期的に見て非常に役立ちます。
ネズミがマンションに現れる大きな理由のひとつが、「食べ物の放置」です。
台所や冷蔵庫の中に食品を無造作に入れていたり、スーパーで買ったままの状態で袋ごと置いていたりすると、ネズミにとっては格好のターゲットになります。特に飲食店のように食材が多く出入りする家庭では、より注意が必要です。
食材は、空気を遮断できる「密閉容器」に入れて保管しましょう。
容器の材質はプラスチックでも構いませんが、硬めで噛まれにくい素材を選ぶと安心です。また、ゴミ箱は蓋付きのタイプを使い、特に「生ゴミ」は溜めずにこまめに処理するよう心がけましょう。
定期的な清掃も欠かせません。
食べかすや調理時に飛び散った材料をそのままにしておくと、ネズミを引き寄せる原因になります。床やシンク周りをこまめに掃除し、ネズミが寄り付かない清潔な環境を保つことが、もっとも現実的で効果的な予防策です。
ネズミは嗅覚が非常に敏感な動物です。
人間にとって心地よい香りでも、ネズミにとっては強い刺激となることがあります。特に「ペパーミント」や「ラベンダー」などの天然の香りは、ネズミが苦手とする代表的な香りです。
香りの活用方法としては、部屋の隅やネズミが通りそうな場所、たとえば電線のまわりやエアコンの配管まわりなどにアロマオイルを含ませたコットンや専用の忌避剤を設置する方法があります。これにより、ネズミがその場所を避けるようになります。
ただし、香りの効果は時間とともに薄れてしまうため、「持続的に効果を保つ」ためには定期的に香りを補充することが重要です。
音もなく忍び寄るネズミの足音や鳴き声が聞こえる前に、香りでしっかりと侵入をブロックしましょう。
現場に伺うと、『ちゃんと掃除していたのに…』『ゴミは毎日捨てていたのに…』とおっしゃる方がよくいます。実際に調査すると、エアコン配管の小さな隙間が放置されていたり、買い物袋ごと床に置かれた食品から匂いが漏れていたりと、“ほんの小さな油断”がきっかけになっているケースが多いんです。
あるマンションでは、台所にペットフードを袋のまま保管していたため、そこがネズミの餌場になってしまいました。別のお宅では、香りの忌避剤を置いていたのに、補充を忘れて効果が切れた途端に再侵入されてしまったこともあります。
こうした経験から言えるのは、『特別なことをするよりも、日常の小さな対策を継続すること』が一番の防御になるということです。隙間を塞ぎ、食べ物をしっかり密閉し、環境を清潔に保つ──地味に思えるかもしれませんが、実際に再発を防いできた多くの現場で共通しているのは、この基本の徹底でした。

害獣プロテクト
川島大知
もしマンション内でネズミを見つけたら、放置せず、すぐに対応することが肝心です。ネズミは一度住み着くと、あっという間に数を増やし、建物全体に影響を及ぼすおそれがあります。
ここでは、管理会社への連絡と専門業者への依頼手順について詳しく解説します。
ネズミを発見した際、最初に行うべきは「管理会社への連絡」です。
これは分譲マンションでも賃貸マンションでも同様で、建物の管理全体を担っている管理会社や管理組合に状況を報告することが、最もスムーズで確実な方法です。
連絡時には、「いつ・どこで・どのような状況で」ネズミを見かけたのかを具体的に説明しましょう。例えば、「○月○日、夜10時ごろに自宅ベランダのケーブル付近で黒いネズミを1匹見ました」といった具合に、明確な情報を伝えることが重要です。
また、緊急時でもすぐに連絡できるように、日ごろから管理会社の電話番号や担当者の連絡先を確認しておくと安心です。エリアによっては、ビル全体の管理会社が別に設定されている場合もあるため、自分の住んでいるマンションの管理形態を把握しておきましょう。
マンションでは、ネズミの問題は共有部分にも関わるケースが多く、住人一人だけで解決するのは難しいこともあります。早期に管理会社と連携し、建物全体で対応することが、被害の拡大を防ぐ鍵となります。
管理会社に連絡した後、必要に応じて「専門業者へ依頼」することも検討しましょう。プロによるネズミ駆除は、根本的な原因への対処や再発防止に非常に効果的です。
まず、「どの業者に依頼するか」を決めるために、業者選びの基準を確認しましょう。
施工実績が豊富か、利用規約が明確に示されているか、料金が適正かどうかといった基本情報はもちろん、実際に依頼した「お客様の声」や口コミも参考になります。最近では、駆除業者を紹介するサイトも多くあり、自分のエリアに対応している会社を簡単に探すことができます。
次に、「見積もりを依頼」するステップに進みます。
いきなり契約を結ぶのではなく、料金の目安や施工範囲、作業時間などについて詳しく相談しておくと安心です。特に、工事の内容が建物の共有部分に及ぶ可能性がある場合は、管理会社との連携が必要になることもあります。
最後に、実際に依頼する前に「作業内容をしっかり確認」することが大切です。
どのような方法で駆除を行うのか、再発防止策としてどんな対処をしてくれるのかを確認し、自分自身が納得してから依頼するようにしましょう。
信頼できる業者であれば、施工前に丁寧な説明や、必要に応じた追加提案も行ってくれます。
実際の現場でよくあるのは、『見かけたけど様子を見ていたら、気づいたら天井裏に巣ができていた』というケースです。ネズミは1〜2匹見かけただけでも、すでに数匹単位で住みついていることが多いため、“放置が一番の失敗”だと私たちは痛感しています。
また、管理会社に連絡したけれど、『共有部分じゃないから対応できない』と言われて困り果ててご相談いただくこともあります。あるご家庭では、最初はベランダで見かけただけでしたが、対応が遅れた結果、配管を通じて隣室にも被害が広がってしまいました。マンションでは“個人の問題”が“建物全体の問題”にすぐ発展するのが怖いところです。
だからこそ、まずは管理会社に連絡しつつ、専門業者に調査を依頼するのが最も確実な流れです。私たちも現場では、被害が広がる前に動いてくださった住民の方ほど、最小限の対策で解決できています。小さなサインでも見逃さず、早めに相談していただければと思います!

害獣プロテクト
川島大知
ネズミを見つけたからといって、すぐに業者を呼ぶのはちょっと勇気が要りますよね。特に気になるのが「費用」と「誰が支払うのか」という点ではないでしょうか。
ここでは、ネズミ駆除の料金相場と、費用の負担ルールについて詳しく解説します。
ネズミ駆除の費用は、「どこに住んでいるか(地域)」や「どんな業者に依頼するか」によって大きく異なります。
たとえば、東京都のような都市部では人件費が高いため料金も高くなる傾向にあり、逆に地方では比較的安く済むこともあります。相場としては、軽度の対応であれば1万円前後、本格的な駆除や再発防止対策を含めると3〜5万円程度になるケースが多いです。
ただし、「高い=安心」でもなければ、「安い=効果がない」とも限りません。
重要なのは、費用に何が含まれているかをしっかり確認すること。
例えば、再発防止策、侵入口の封鎖作業、清掃や消毒、アフターフォローの有無など、それぞれの業者によってサービス内容は異なります。
また、複数の業者に見積もりを依頼するのも良い方法です。同じような状況でも、提示される料金には差が出ることが多く、「あれ、こんなに高くなるの?」と思う前に、比較検討することで納得のいく選択ができるでしょう。
特に1階に住んでいる方や、気温が下がる秋から冬にかけてはネズミの活動が活発になりやすく、被害の報告も増えます。早めに行動しておくことで、無駄な費用をかけずに解決できる可能性も高まります。
実際にネズミ駆除を行う場合、「費用は誰が負担するのか?」という問題が浮上します。これは集合住宅特有の悩みであり、住人それぞれの立場によって意見が分かれることも少なくありません。
基本的には、「マンションの管理規約」に準じて費用の負担方法が決められています。
たとえば、共用部分(廊下やゴミ置き場など)での被害なら管理組合や管理会社が負担するケースが多く、専有部分(住戸内)での駆除であれば、その住人が費用を負担するのが一般的です。
ただし、住民間での取り決めが明文化されていない場合、「誰がどこまで責任を持つのか」が曖昧になり、トラブルの原因になることもあります。そのため、あらかじめ「被害の範囲」や「負担のルール」を管理組合と確認し、必要であれば他の住民とも話し合っておくことが大切です。
過去の事例を参考にすることも有効です。
たとえば、「ネズミが配管を通じて複数の部屋に被害を及ぼしたケース」では、全体負担として管理組合が費用を出した例もありますし、「住人の過失によって生ゴミが放置され、ネズミが発生したケース」では、その住人に全額負担を求めたという事例も存在します。
被害が大きくなる前に、費用負担のルールを整理しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、スムーズに問題を解決することができます。
費用のことで揉めてしまう現場を何度も見てきました。ネズミを目の前にして不安な気持ちでいっぱいなのに、『うちが払うのか?』『隣と折半すべきじゃないか?』と話し合いが進まず、対応が後回しになってしまうんです。その間にもネズミは増えて、被害が広がってしまう。住民の方が口にされる『お金のことばかり気になって眠れなかった』という言葉が忘れられません。
だからこそ、私たちは駆除の提案をする際、必ず“誰がどこまで負担するのか”を整理するところから始めています。はっきりと決めて動き出せば、被害は最小限で済みますし、住民同士の関係も悪くならずに済みます。お金のことを後回しにせず、まず最初に整理することが、安心を取り戻す第一歩だと実感しています!

害獣プロテクト
川島大知
ネズミを確実に駆除するには、「正しい方法」と「信頼できる業者」の選定が欠かせません。特にマンションのような集合住宅では、個人の努力だけでは完全な対策が難しいこともあります。
ここでは、効果的な駆除方法の種類と、失敗しない業者選びのポイントについて解説します。
ネズミ駆除には、物理的・化学的な手段、そして予防策という3種類のアプローチがあります。それぞれの方法には特徴があり、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。
まず、最も一般的なのが「物理的な駆除方法」です。
これは捕獲器や粘着シートを使ってネズミを直接捕まえる方法で、自力でも比較的簡単に取り組めます。経路が特定できていれば、通り道に設置することで高い効果を発揮します。
ただし、数が多い場合や排水管などの複雑な場所に入り込んでいるケースでは、限界もあるため注意が必要です。
次に、「化学薬品の使用」です。
毒餌や忌避剤など、さまざまな製品が市販されており、害虫駆除と同様に高い効果が期待できます。ただし、使用方法を誤ると人やペットに害を及ぼす危険もあるため、強い成分を使う際には十分な注意が必要です。
特にマンションでは、共有スペースでの使用は管理組合の許可が必要になることもあるため、事前の確認を忘れずに。
そして最後に、もっとも大切なのが「予防策」です。
ネズミを出す前に、再発を防ぐための対策を講じることが、長期的な防除において非常に有効です。隙間を塞ぎ、排水口や通気口の点検を行い、食べ物を放置しないよう管理することで、ネズミが住み着く環境を断つことができます。
これら3つの手段を組み合わせて行うことが、完全な駆除につながります。
効果的にネズミを駆除するには、専門の業者に任せるのが最も確実です。しかし、「どの業者に依頼すればいいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、以下のポイントを参考にすると、信頼できる業者を探しやすくなります。
まずは「口コミや評価」を確認すること。
過去に利用した人の感想は、その業者の信頼性や対応力を判断する大きな手がかりになります。特に、対応の早さや作業の丁寧さに関する評価が高い業者は安心です。
次に、「見積もりの透明性」も非常に重要です。
料金が明確に提示されているか、作業内容と金額のバランスが取れているかをチェックしましょう。不明瞭な追加料金が後から発生しないよう、事前に細かく確認しておくことが、トラブル防止につながります。
さらに、「アフターサービスの有無」も選定の決め手になります。
万が一、再発した場合に無料で対応してくれる保証制度がある業者や、定期点検を実施してくれるプランを提供している業者は、長期的な安心感が得られます。
最近では、ネット検索で「ネズミ駆除 業者」などと入力するだけで、地域ごとの業者が簡単に見つけられる便利なサイトも多数存在します。こうしたサービスを活用すれば、自分にとって最適な選択肢を効率的に絞り込むことができます。
一方で、「裁判沙汰になったトラブル業者」なども稀に存在するため、実績や対応エリア、利用者の声を丁寧に調べ、慎重に選ぶことが大切です。
“方法”も“業者選び”も、現場では順番を間違えると長引きます。たとえば、粘着シートだけ先に大量に置いて学習させてしまい、のちの捕獲効率が落ちた例や、毒餌で一時的に静かになったもののダクト内で死骸が発生して悪臭とハエの二次被害…マンションでは本当に起こります。共用部に薬剤を使うと管理規約に抵触することもあるので、自己判断はおすすめしません。
私たちが必ず守る流れは、①徹底調査(糞の新旧・齧り痕の色・ラットラン=黒光りの通路・配管貫通部/PS扉/通気口の2cm隙間を洗い出す)→②追い出し・捕獲(通路“線”に沿った設置、餌の鮮度管理)→③封鎖(ステン網・鋼板で“面”で塞ぐ)→④清掃・消毒→⑤再点検です。どこか一つでも抜けると、必ず戻ってきます。
業者選びで現場で差が出るのはここです。見積もりを電話だけで即提示、当日契約を急かす、施工前後の写真や“封鎖マップ”を出さない、保証の範囲と再訪費用が曖昧——こうしたところは避けてください。逆に、現地で調査した担当者=施工者、封鎖材の“材質と枚数”、封鎖箇所の位置図、清掃消毒の範囲、再発時の無償対応条件(期間・回数・出張費の扱い)まで紙で明示できる会社は信頼できます。迷ったら、複数社で封鎖箇所数・材質・保証条件を並べて比べる。これが、住民の方にとって被害を長引かせないいちばん“現実的な”選び方です。

害獣プロテクト
川島大知
ネズミを駆除したからといって安心してはいけません。
ネズミは繁殖力が非常に高く、再び侵入してくる可能性があります。今回の駆除を「一時的な対処」で終わらせず、長期的な予防と点検を行うことが、再発を防ぐためには必要不可欠です。
まず最初に取り組むべきは、ネズミの「侵入口となる場所」を徹底的に確認し、隙間や穴をしっかりと塞ぐことです。
繁殖力が強いネズミは、たった1匹でも放置すれば、関東のような温暖なエリアではあっという間に大量に増えてしまいます。配管の周囲やベランダの隅など、見落としやすいポイントにも警戒しましょう。
次に重要なのが「食べ物の管理」です。
食品は必ず密閉容器に保管し、食べかすや生ゴミをそのままにしないことが、餌の供給源を断つ基本です。冷蔵庫に入っていない食材は特に注意が必要で、飲みかけのジュースや開封済みのスナック菓子も、ネズミにとっては魅力的なターゲットになります。
さらに、「衛生管理の徹底」も忘れてはいけません。
台所やダイニングの床、シンク下などは定期的に清掃を行い、足跡やフンが残っていないかを確認することが大切です。ネズミは清潔な環境を嫌うため、日々の掃除が有効な予防策となります。
このように、ネズミの再侵入を防ぐためには、いくつかのチェックポイントを押さえて日常的に行動することが不可欠です。
ネズミの再発を未然に防ぐためには、「定期的な点検」が非常に重要です。
まず、自分で定期的に建物の中をチェックする習慣を持つことが大切です。排水口の周囲、ベランダ、食品保管場所などを定期的に調査し、異変がないかを確認しましょう。
また、自分での点検が難しい場所や判断が困難な場合は、「専門家による定期点検サービス」を利用するのもおすすめです。プロによる点検では、一般的な見落としがちな箇所も含め、徹底した確認が行われるため、再発防止の精度が高まります。
特に、ネズミが原因で起きる「火災」や「建物の破損」は、最悪の場合、大きな責任問題に発展するリスクもあるため、定期点検は費用をかけてでも実施する価値があります。
点検の頻度は、少なくとも年1回は行うのが一般的です。ネズミの活動が活発になる季節(秋〜冬)を目安にしておくとよいでしょう。
早期発見と早期対応が、被害を最小限に抑える鍵となります。
駆除が終わった直後のお客様からよく聞くのは『これで安心しました』という声です。でも、私たちの経験上、本当の勝負はその後なんです。実際、半年後に『また足音がする』と連絡をいただき調査に入ったら、以前とは別の隙間から新たに侵入されていた…そんなケースは珍しくありません。
あるマンションでは、最初の駆除後に清掃と封鎖をきちんとやったのですが、住人の方がベランダにペットフードを一時的に置いたことがきっかけで、再びネズミが寄りついてしまいました。ほんの小さな油断や見落としが、再発につながることを現場で痛感します。
だからこそ私たちは、駆除完了の報告をするときに必ず『定期点検と日々の習慣が再発防止の鍵です』と伝えています。点検を年1回でも続けているご家庭は、ほぼ再侵入がありません。駆除で終わらせず、その後のケアをどこまでやるかで、安心できる生活が守れるかどうかが決まります!

害獣プロテクト
川島大知
ネズミの発生は、突然の出来事として多くの住人を驚かせます。
ここでは、実際に寄せられることの多い質問とその対応方法について解説します。正しい知識を持つことで、トラブルを未然に防ぎ、安心して暮らせる環境づくりにつなげましょう。
マンションでネズミが出た場合、まず大切なのは「冷静に状況を確認する」ことです。
突然の発見に驚いてしまうかもしれませんが、パニックになると対応が遅れてしまい、さらなる被害につながる恐れがあります。
次に、「どこでネズミを見かけたのか」を明確にし、その周辺にある隙間や穴、床下の通気口、換気扇のまわりなど、侵入経路と思われる場所をチェックしましょう。
侵入したネズミが配線をかじってしまうと、火災などの二次トラブルが起こる可能性もあるため、放置は厳禁です。
また、同じ建物内に住んでいる他の住人にも「ネズミが出没した」ことを共有することが大切です。自分の部屋だけの問題ではなく、集合住宅全体で対応しなければならないケースが多いため、周囲との連携が被害を最小限に抑える鍵となります。
誤って殺鼠剤やガスなどの化学薬品を自己判断で使用すると、ペットや人への影響が出ることもあるため、正しい知識と対応が求められます。
ネズミが頻繁に出る、あるいは自力での対応が難しいと感じた場合は、早めに「駆除業者に依頼する」ことを検討しましょう。
ただし、業者の選び方を間違えると、効果が得られないだけでなく、高額な料金を請求されるなどのトラブルに発展する可能性もあります。
まずは「信頼できる業者かどうか」を判断するために、利用者の口コミや2024年以降の新着レビューをチェックすることをおすすめします。特に、作業の丁寧さやアフターサービスの充実度に関する意見は、判断材料として非常に有効です。
次に、「料金の透明性」を確認しましょう。
見積もりが曖昧で、追加料金が次々と発生するような業者は避けるべきです。作業範囲や費用の内訳が明確に提示されているかを比較し、信頼できる業者を選びましょう。
また、「アフターサービスの有無」も重要なポイントです。
一度駆除しても、ネズミが再び室外機やエアコンのダクトなどから入り込んでくることは珍しくありません。こうした再発リスクに備えて、定期的な点検や再施工が含まれるサービスを提供している業者を選ぶと安心です。
万が一のトラブルに備えて、契約内容や保証条件についても事前に確認し、不安がある場合は弁護士などの専門家に相談するのも一つの手です。
ネズミが出たとき、多くの方が口にされるのは『恥ずかしくて人に言えなかった』『自分の部屋だけの問題かと思った』という言葉です。でも、実際にはマンションという建物全体に関わることが多く、黙って抱え込んでしまうと被害が広がってしまうんです。
過去には、最初に発見した住人の方が誰にも相談できずに数か月が経ち、その間に天井裏の配線がかじられて停電トラブルにまで発展したケースがありました。もっと早く声を上げてくだされば…と残念に思うこともあります。
私たちからお伝えしたいのは、『一人で悩まず、必ず周囲と共有してほしい』ということです。管理会社や業者に相談するのはもちろんですが、まずは“自分だけの問題ではない”と意識することが、解決の第一歩になりますので、まずはご相談だけでも構いませんので、お気軽にお問合せください!

害獣プロテクト
川島大知
ネズミ被害は、いつどこで発生するかわかりません。特に集合住宅であるマンションでは、自分の部屋だけの問題では済まず、建物全体に影響を及ぼす可能性があります。
だからこそ、日常的な対策と知識の共有が大切なのです。
ネズミは非常に繁殖力が高く、一度入り込んでしまうと短期間で個体数が大きく増えてしまいます。そのため、「早期発見」と「迅速な対処法」が被害を最小限に抑えるうえで極めて重要です。
マンション内で異変を感じたら、ネズミの足跡やエサの食べ残しなど、小さなサインでも見逃さずに確認しましょう。特に2025年のような寒さが厳しい季節には、温かい屋内を求めてネズミが侵入してくるケースが多く、対処が遅れると状況はさらに悪化します。
早めに対策を講じれば、感染症やアレルギーなどの健康リスクを軽減することができるほか、駆除にかかるコストも少ない金額で済む可能性が高くなります。大きな被害が出てから対処するのと比べ、初期の段階での対策には、メリットがたくさんあるのです。
ネズミ対策を成功させるためには、「まず相手を知ること」が出発点です。
ネズミの生態や侵入経路、好む環境などを理解することで、自分の住宅に合った具体的な予防策が見えてきます。たとえば、食べ物の管理を徹底することや、壁の隙間を封鎖することは、多くの家庭で有効な方法です。
また、自分だけで全ての対応をするのではなく、周囲の住人とも情報を共有し合いましょう。
同じ建物内で暮らす以上、連携して動くことがトラブルを防ぐ鍵となります。「あの部屋で見かけた」「この辺にフンが落ちていた」といった小さな情報でも、全体の対策に役立ちます。
マンションという空間で安心して暮らすためには、ネズミ対策を“他人事”にせず、ひとりひとりが意識を高めることが必要です。このような意識が広がれば、home(住まい)としての住宅の価値が上がり、地域全体の暮らしの質も向上していくでしょう。
ネズミの問題は、ただの「害虫対策」にとどまらず、安心・安全な暮らしを守るための重要な取り組みなのです。
マンションのネズミ対策で一番強く感じるのは、“早く気づいた人が声を上げるかどうか”で結果が大きく変わるということです。実際に、廊下でフンを見つけてすぐに管理会社へ連絡してくれたおかげで、初期対応で封鎖でき、最小限の費用で収まった例もあります。逆に、『自分の部屋だけだから…』と数か月放置した結果、天井裏全体に巣が広がり、建物全体で大規模な工事が必要になったこともありました。
現場を見ていて思うのは、ネズミの問題は“個人の生活空間”を超えて、建物や住民同士の関係性にまで影響するということです。だからこそ、異変を感じたら一人で抱え込まず、周囲と共有して早めに行動することが、安心した暮らしを守る何よりの近道なんです!

害獣プロテクト
川島大知
近年、マンション居住者の間で注目が高まっているのが「環境や健康に配慮したネズミ駆除」です。従来のような強い化学薬品や殺鼠剤を使う方法に抵抗を感じる方も増えており、より安全で持続可能な対策が求められています。
例えば、天然成分由来の忌避スプレーやペパーミントオイルを活用した対策は、ネズミにとって強い刺激となる一方で、人間やペットには無害で、環境にも負荷が少ないのが特徴です。
最近では、ハーブ由来の粒状忌避剤や、生分解性の高い封鎖用シーリング材なども市販されており、簡単に取り入れられるようになっています。
また、欧州や北米で広がっている「生態系保全型ネズミ防除」の考え方では、ネズミを殺すのではなく、住み着けない環境をつくることに重点が置かれています。これは、日本でも今後注目される可能性が高く、管理会社やマンションの管理組合にとっても、環境負荷の少ない方法として採用が期待されています。
これらのエコ対策は、家族やペットの安全を守りつつ、マンション全体の環境価値を高める新しいアプローチとして、今後さらに注目されていくでしょう。
ネズミ対策は通年必要ですが、実は「季節によってネズミの行動パターンやリスクレベル」が大きく異なることをご存知でしょうか?これを把握することで、より効果的な予防と駆除が可能になります。
春は繁殖期の始まりで、ネズミが巣作りのために活発に動き始めます。この時期に屋内への侵入が増えるため、配管や通気口などのチェックと封鎖が特に重要です。
夏は比較的リスクが低い時期とされていますが、エアコンの使用が増えることで、室外機や排水ホース周辺が侵入経路になることがあります。湿気を好むドブネズミが出没するケースもあるため、油断は禁物です。
秋になると寒さを避けるために、ネズミの屋内侵入が急増します。特に関東などの都市部では、食べ物を探してマンション内を徘徊する事例が多発するため、この時期こそ重点的な対策が必要です。
冬は、繁殖はやや落ち着くものの、暖かい室内はネズミにとって魅力的な空間となるため、冷蔵庫裏や床下など見えない場所への侵入が増加します。この時期は定期点検を欠かさず、侵入口の再確認を行いましょう。
季節に応じた予防策を行うことで、ネズミの発生リスクを大幅に減らすことができます。
近年、ネズミ対策にもテクノロジーの波が押し寄せています。
従来の「見つけてから駆除する」方法に代わり、IoT技術やスマートセンサーを活用して「常時監視・早期発見」を可能にする新しい管理手法が登場しています。
たとえば、ネズミの動きを感知する赤外線センサー付きの小型カメラを共用部に設置することで、人目の届かない夜間でもネズミの出没をリアルタイムで確認できます。特に配線や換気ダクト、天井裏など、侵入しやすく目視が困難な場所では非常に有効です。
さらに、センサーとクラウドサービスを連携させれば、ネズミの移動パターンや発生場所の「データ可視化」が可能になります。これにより、管理会社や専門業者は効率的に対処でき、住民への説明責任や対応の透明性も向上します。
一部の高級マンションでは、すでにこうしたスマート監視システムを導入しており、害虫・害獣対策の「新常識」として注目を集めています。
今後は、予算や規模に応じて中規模の集合住宅にも普及していくと見られ、マンションの価値向上や住民の満足度向上にもつながるでしょう。
CONTACT
天井裏や屋根裏の現地調査(写真撮影調査付き)は無料です。
現地調査後に依頼に至らなくても費用は発生しません。
対応地域
大阪府、京都府、滋賀県、和歌山県、兵庫県、奈良県、岡山県の全域対応。
(詳細地域はこちら)